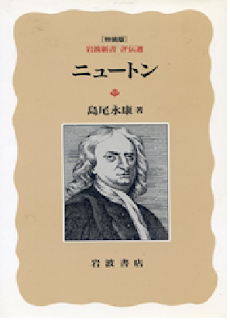2012年にチリで制作された映画で、1973年から17年間続いた軍事独裁政権の崩壊を、コマーシャル映像の制作という視点から描いています。
チリは、すでに16世紀の前半にスペイン人が進出し、先住民と戦いながら、比較的安定した農場経営が行われてきました。19世紀前半にスペインから独立し、胴と硝石が豊富に産出したことから、経済的にも安定し、中南米の他の国と比べて、比較的民主政治が発展し、他の国に比べて軍事クーデタもあまりありませんでした。ただ、他の中南米諸国と同様に、一次産品の輸出に依存していたため、国際価格の影響を受けやすく、経済構造が脆弱でした。また、また地主による土地支配や、外国資本による鉱山の支配にも、不満が高まっていました。
そうした中で、1970年に人民連合のアジェンデが大統領に当選し、チリに社会主義政権が成立します。それは、世界初の民主的選挙によって成立した社会主義政権ということです。アジェンデは帝国主義による従属からの独立を掲げ、キューバとの国交を回復、鉱山や外国企業の国有化、農地改革による大土地所有制の解体などを行いますが、稚拙な経済政策のため経済は混乱します。また、西半球に第二のキューバが生まれることを恐れていたアメリカは、CIAを使って反政府活動を支援したため、社会は一層混乱しました。
そうした中で、1973年9月11日に、アメリカの支援を受けたピノチェト将軍がクーデタを起こし、銃撃戦の末にアジェンデは自殺します。9.11といえばアメリカでは同時多発テロを想起しますが、チリではピノチェトのクーデタを想起するのが普通だそうです。ピノチェトは反対派を徹底的に弾圧し、彼が支配する17年間に、数千から数万人の人が殺され、数十万人が強制収容所に送られ、さらに国民の10分の1に当たる100万人が国外亡命したとのことです(ウイキペディア)。そして、これらの弾圧は、同じ頃独裁政権が成立していたアルゼンチンなどの「汚い戦争」と連動していました。
しかし、1980年代に、周辺諸国で民主化が進む一方で、チリでは相変わらず人権侵害が続けられており、ピノチェトに対する国際世論の批判が高まってきました。そこでピノチェトは、国際的な批判を逸らすために、1988年に国民投票で自らの政権の信任を問うことにしました。その投票とは、ピノチェトの任期を8年延長することに対する「イエス」か「ノー」というものでした。かなりいい加減な国民投票であり、しかも国民は長く続いた独裁政治に対して諦めおり、どうせ最後は政府が投票結果を操作すると思っていました。したがって、政府も国民を、当然、結果は「イエス」が多数を占めると考えていました。しかしこれだけでは国際世論を納得させられないので、投票日までの27日間、イエス派とノー派がそれぞれ深夜に15分だけTVコマーシャルを流すことが認められました。深夜にテレビを観る人はいないだろう、という考えでした。
映画は、ここから始まります。広告会社に勤めるレネにノー派からの広告の制作依頼がきますが、同時に彼の上司にイエス派からの制作依頼もきます。つまり同じ会社の中で、両派の広告を制作することになったわけです。政府からすれば、同じ会社の上司がイエス派の広告を制作すれば、同時にノー派の広告内容も知ることができるというメリットがありました。総じてイエス派は甘くみており、イエス派のために制作された広告は、北朝鮮の国営放送のようで、ピノチェトを称賛するだけの映像でした。
これに対して、レネの周囲の人々はピノチェトを非難する広告を期待していましたが、レネは広告は明るいものでなければならないと確信しており、楽しい家族のピクニックの場面や、美女たちを勢揃いさせる場面などをおり込み、時にはユーモアを交えつつ、人々に明るい未来を予感させるような広告を制作します。この広告は、諦めていた人々を目覚めさせ、自分の一票の大切さを自覚させます。政府は危機感を感じ、レネにいろいろな嫌がらせをしますが、結局投票では「ノー」が多数となります。もちろん、ピノチェトは結果を無視することもできたでしょうが、ピノチェト政権の生みの親ともいうべきアメリカもピノチェトを批判しており、退陣するしかありませんでした。1988年は、冷戦終結の前年であり、もはやアメリカにとってピノチェトは無用の存在となっていたのです。
映画で観る限り、レネには政治的な関心はあまりなく、純粋にコマーシャル制作者の視点で、このコマーシャルの制作にあたりました。そしてそれが歴史を動かしたのです。しかし、コマーシャルが歴史を動かすということが良いことなのでしょうか。ヒトラーの独裁権力は政治宣伝によって生み出されたものであり、コマーシャルによって民衆を動かすということは、決して好ましいとはいえません。このことについては、この映画の制作者も理解しているようで、最後に、依頼された仕事を終えたレネの姿を淡々と描いています。彼は、コマーシャル制作者としての仕事をしただけなのです。そしてそれは、結果的にチリを独裁から救ったのです。
その後のチリの歩みは、決して平坦ではありませんでした。相変わらず、経済不況に見舞われると政権が不安定になるという構造的な問題を抱えていますが、しかし独裁政治にもどることはありませんでした。一方、ピノチェトは、退陣後も終身上院議員として隠然たる影響力を持ち続けますが、やがて「人道に対する罪」で訴えられ、さらに巨額の不正蓄財が明るみに出ますが、高齢と病気のため罪状は棄却され、2006年に病没しました。91歳でした。